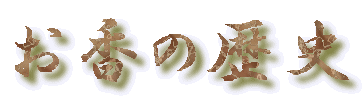 |
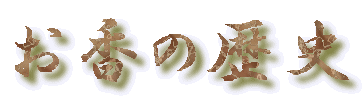 |
| 香木の日本への渡来は日本書紀によれば推古三年(595年)となっています。 「推古三年夏四月沈水が淡路島に漂ひ着けり。甚大き一圍、島人沈香しらず、薪に交て寵に焼く、其煙気遠く薫る、即異なりとして献る」 と記述されています。 一圍(ひといだき)もある流木を島人がかまどに焼いたところ、芳薫に驚いて「即異なりとしてそれを献る(たてまつる)」と書かれています。 これが正倉院の宝物として伝承の蘭奢待(らんじゃたい)となるわけです。 ただ、これに先立ち、大和の古寺には柄香炉(えこうろ)など仏教祭具としての香具が伝承するから、仏教の渡来とともにもたらされたと考えるのが自然であります。 当時は仏事のほか、薬用として、薫物(現在の香水のかわり)として着物に香りを焚き染めるいう使い方であったようです。 仏教公伝は百済聖明王(くだらせいめいおう)の宣化三年であるが、百済には、四世紀後半に伝わっているから、実際には、公伝以前に伝来は考えられています。 茶と香は最初から仏様への供え物です。 天平元年「行茶之儀」が知られる程度で宮中の儀式に焼かれるのみです。 奈良時代も終わろうとする天平勝宝六年ころ、鑑真の渡来により仏典とともに沈香、安息香など種々の、香料、蜜と薬の調合により「薫物」をつくる法を伝えました。 宗教儀式に用いられた香は、平安時代になると、貴族達が生活を楽しむために愛用されるようになりました。
平安の始め嵯峨・淳和両朝に、右大臣/左大臣を歴任し勧学院を創設した、閑院左大臣藤原冬嗣は、 薫物の「梅花」・「侍従」・「黒方」を、つづいて右大弁源公忠が「荷葉」を創案。 「菊花」・「落葉」も同じ頃ですが作者は不明です。 今でも薫物は基本的にこの六種(むぐさ)以外ほとんど用いられません。 薫物は「たきもの」とよみ、現在も用いられる練香にあたり、沈香や丁子・白檀・甲香などの香木を粉末にして、好みの応じ麝香(じゃこう)などを加え、梅肉や蜂蜜で練り固めたものです。 これらの処方は、それぞれ工夫して秘密につくられ、家代々に伝えられました。 やがて、薫物のもつ幽玄な香りをたき較べて鑑賞し、優劣を競う「薫物合」(たきものあわせ)という遊びに発展していきました。
|
||||
|
鎌倉時代に入る前後には、体身香(たいしんこう)という、香木、香料を服用することで自分の身体から香りを発するという事も存在しました。 鎌倉時代は武士の禅的美意識と無常観により、平安の薫物文化から一転、沈香一木をくゆらすを好む文化への変化が生じます。二種以上の香木を用いる「組香」(くみこう)に発展し、「名香合」(めいこうあわせ)といわれるものになります。
応永期頃から官家・公卿とその周辺の日記に御所や御内儀で十種香などが催されたとされています。 十六世紀に入り線香の製法が中国大陸から朝鮮半島を通って堺へ入ってきます。 香遊びが香道として発達したのも、おそくともこのころ(十六世紀末頃)と伝えられ、従来公家の間で行なわれていた香の催しが一般にも普及し始めたのに伴い、公家では、宮中で香をつかさどる御香所の職にいた、三条西実隆が、武家では、足利義政の命によって沈香の研究をした志野宗信、また、文人では、宗祇や肖柏らによって香道の基礎がつくられました。
江戸時代に香木の分類、六国五味(りっこくごみ)が完成しました。 元禄の頃、芸能の勃興とともに家元制が確立されていきました。 享保・元文ころには、香道も完成時期に入り道具・教授の階梯も整備されます。 幕末から明治期は、衰退を余儀なくされ、戦後茶道の隆盛に牽引されるかたちで現在の流行に至る訳です。 |
| トップページに戻る ■念珠 ■こだわりの仏像 ■香りの世界 ■お寺の情報 ■巡礼 ■写経のすすめ ■リンク ■お話しましょ |
|
|
Copyright(c)2003NENJUDO All rights reserved. |